
NHK〈Eテレ〉で『音楽はかつて“軍需品”だった 〜幻の楽譜に描かれた戦争〜』が放送される。戦後80年の今年2025年、音楽と戦争について考えるドキュメンタリーだ。
NHKの倉庫で見つかった戦時下の楽譜を基に、幻の曲が再現された。政治学者で音楽評論家の片山杜秀さんが、音楽を通して戦争の時代を見つめる。黒柳徹子さんの証言なども交え、音楽が軍需品として使われた時代をひもとく。
再現された曲は、島根県出身の声楽家、田中俊太郎(たなか しゅんたろう)さんが出演して歌唱など行う。
田中さんが歌うのは、山田耕筰(やまだ こうさく)が、沖縄戦終了後に書いた「沖縄絶唱譜」だ。山田耕筰は童謡「赤とんぼ」の作曲で知られる。「沖縄絶唱譜」は、これまで楽譜が公にされおらず「幻の名曲」だった。
田中さんは歌手として活躍するかたわら、研究活動を行う「音楽研究家」でもある。大学では博士課程を修了し、博士の学位を取得している。
田中さんの研究は、1930年代以降に作られた日本の音楽作品が中心だ。戦時中も対象としているため今回の番組は、田中さんの研究分野と重なるところがある。
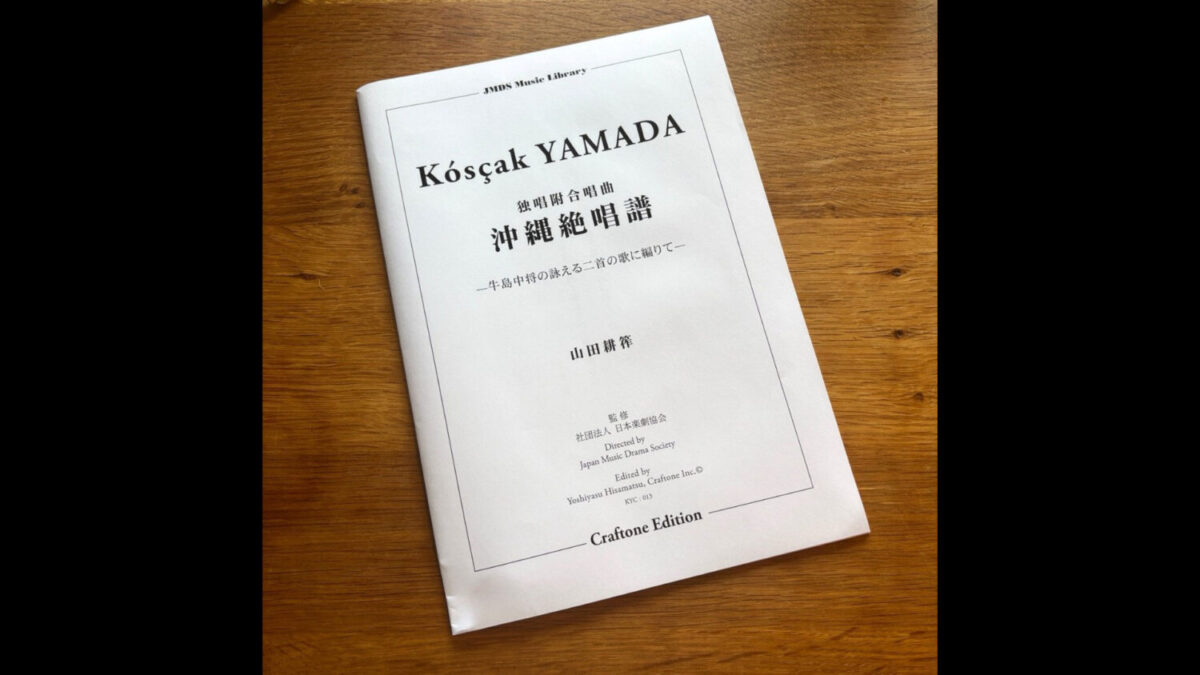
【田中俊太郎さん所有(番組で使用されたものではありません)】
番組では高木東六(たかぎ とうろく)が作曲した「たのしい食卓」や「更けゆく夜」も取り上げられる。
高木東六は、現在の鳥取県米子市で生まれた作曲家だ。「水色のワルツ」などの曲で知られる。出身地は岡山県とされることもある。本人が書いた著書によると、戸籍の登録が父の故郷である岡山県になっているためだという。
著書によれば、生まれてすぐに岡山県の家に預けられている。父は東六が4歳のころまで、米子でロシア正教の宣教師をしていた。
東六は作曲家となった後、米子市制40年のときに「米子市の歌」を作曲した。鳥取県立米子高等学校の校歌や、王子製紙米子工場の社歌も作曲するなど、鳥取県とのゆかりが深い。1968年(昭和43年)に島倉千代子さんが「裏大山小唄」という、鳥取県江府町をPRするレコードを発売している。作詞作曲は高木東六だ。東六は、後に米子市の市民栄光賞を贈られている。
番組では、山田耕筰や高木東六の曲以外に、大木正夫が作曲した「漢口進攻」や、齋藤秀雄が作曲した「二千六百一」なども紹介される。
田中さんは「沖縄絶唱譜」を独唱し、「漢口進攻」では朗読と独唱を担当する。
放送に先立ち、田中さんは次のように述べた。
「私が演奏した《沖縄絶唱譜》は、敗戦間際の沖縄戦で奮闘した、牛島中将の辞世の句に作曲されました。そこにあるのは絶望的な状況においても、なお守ろうとするものがある人間の祈りでした。番組を通じて、当時の音楽文化について、戦争について、平和について一緒に考えていただけると嬉しいです」
『音楽はかつて“軍需品”だった 〜幻の楽譜に描かれた戦争〜』は、2025年8月16日午後10時から放送される。
関連記事




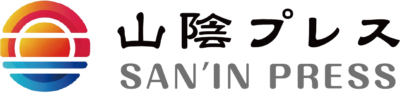





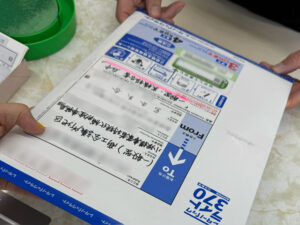
-300x153.png)
