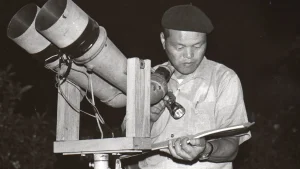2024年11月、認知症の女性は「いまがいちばんたのしい」と涙をながした。70歳代だった。介護施設でのできごとだ。マイクの前に立つ男は、人のために歌えたという喜びを感じた。自分の音楽が人の役にたっていると思えた。いちどはプロになる夢をあきらめた。それから21年後のことだ。
尾上明範(おのえ・あきのり)さんがギターを始めたのは、15歳のときだった。エリック・クラプトンやカーペンターズにあこがれた。アマチュアバンドに入ることもなく、学園祭のステージにたつこともなく、ひたすら趣味としてギターを楽しんだ。将来「歌手」になるとは思っていなかった。
伊勢正三さんやチューリップのカバーをひとりで歌った。恥ずかしがり屋で人前に立つことなど考えられなかった。いつも人前で歌うことにあこがれていた。
尾上さんは高校卒業後に上京する。音楽の専門学校でギターを学ぶためだった。恥ずかしがり屋だったが、プロの「ギタリスト」にはなりたかった。
1年後、ふるさとへ引き上げた。東京という街のスピード感が合わなかった。人と話すことが苦手で、新しい環境に馴染むのにも時間がかかった。
ふるさとに帰ってアルバイトばかりしていたとき、もう一度プロに挑戦したいと思いなおした。21歳のときに再び東京へ向かった。
尾上さんの父はジャズやフュージョンを演奏するプロのミュージシャンだった。しりあいに野秋聖子(のあき・きよこ)さんというシャンソンのピアニストがいた。野秋さんにプロになりたいと相談したところ、シャンソンを歌ってみないかと提案された。
尾上さんはギタリストになりたかったが、もともと歌うことは好きだった。はじめて人前で歌ったのはシャンソンのライブハウスだった。観客は20人ほどだったが、緊張で手足がふるえた。
再び上京してからの1年間は、活動のやり方が分からず途方に暮れた。2年ほどしてライブハウスのオーディションに合格した。弾き語りの歌手が集まるライブハウスだった。以来プロのシンガーソングライターとして全国各地でライブを行っている。
尾上さんは作詞や作曲も得意としている。2012年5月にはアメリカのラジオ局で、尾上さんの曲がキャンペーンソングに選ばれた。「手紙」という曲だ。東京でオーディションが行われて、観客の投票で決まった。

尾上さんを歌の世界に導いてくれた野秋聖子さんは、音楽療法士でもある。尾上さんが福祉施設で歌い始めたのも野秋さんがきっかけだった。
障がいのある子どもに歌を聞かせてやってほしいと野秋さんに頼まれて、就労支援センターで初めて歌った。2010年の12月に開催したクリスマスコンサートだ。目をそらさず真剣に聴いてくれたことが強く印象に残っている。楽しかったと多くの子どもたちが言ってくれた。
コンサートは近年も続いている。当時、小学生だった子どもたちが大人になり、今も参加してくれる。
尾上さんの母は介護士だった。就労支援センターでのライブについて聞いた母が、ふるさとの介護施設でもやってほしいと言ってきた。
介護施設でライブを行うと、普段ほとんど話しをしない利用者が、楽しそうなリアクションをする。動いていなかった脳の部分が音楽によって刺激されるのだという。
施設の職員は「○○さん、こんなにしゃべるんだ」と、利用者の反応に驚く。尾上さんは自分が逆に力をもらって、もっと頑張ろうと励みになる。
介護施設で人気があるのは「蛍の詩」だ。過ぎ去った夏の思い出を懐かしみながら、胸に切なさがこみ上げる曲だ。
2026年には、初めてプロとしてステージに立ってから、20周年を迎える。尾上さんは充実した20年だったと振り返る。

2025年12月には東京の介護施設でクリスマスコンサートを行う。
介護施設のライブでは、利用者が知っている曲を歌うことが多い。一緒に歌ってくれることも喜びの1つだ。
ふだんは口を閉ざしている人が、音楽を聴いたあとには言葉数が多くなる。高齢者が少年少女のような顔で演奏を聞いてくれるのを何度も目の当たりにした。音楽の可能性を強く感じる。
ライブ会場へ足を運ぶことができない人に音楽を届けたい、という気持ちが強くある。
「ひとつの形として、それができているかなあ」と、尾上さんは福祉施設のライブについて想いを語った。
いちどはプロのミュージシャンになる夢をあきらめた。いまは自分の歌が人の役にたっていると心から思える。
今後は大きなステージで歌うことが夢だ。作詞や作曲の仕事も増やしたい。福祉施設のライブも全国へ広げたい。

関連記事